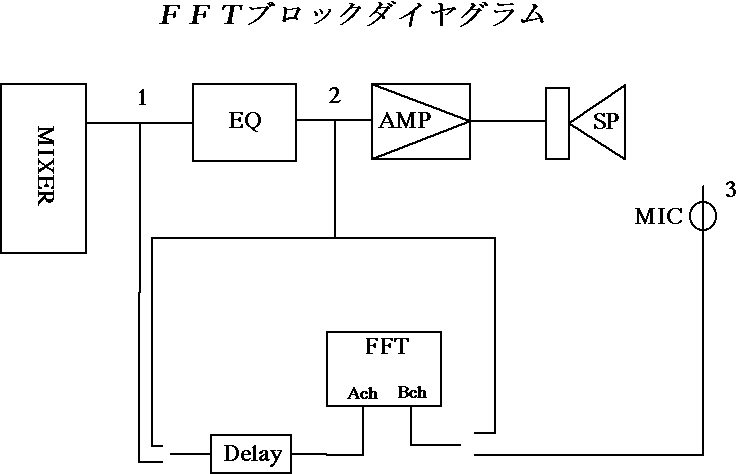
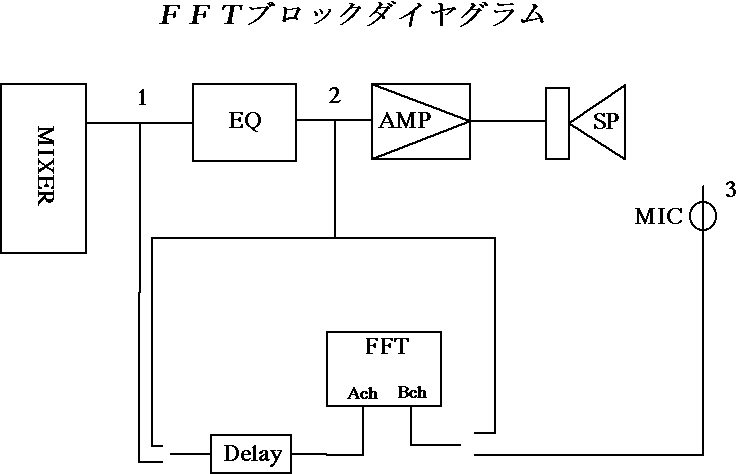
「DUAL−CHANNEL FFTシステムによるサウンドシステムの測定補正法は、演奏者聴衆、
双方にとって、明瞭なオーディオ実現への一助となる。」
ライブ演奏でハウスミキサーはしばしば思いどおりにならない苛だたしさを味わうことがある。
リハーサル中に最適なパフォーマンスを目指して調節し、EQをセットし、サウンドチェックを澄ませたにもかかわらず、実際本番となると貧弱なサウンドクオリティーになってしまうのである。
低域はブーミーだし、中域は鈍い響きだし、高域は単調で冴えない。 一体どこが悪かったのだろう?
公会堂、コンサートホール、スポーツアリーナ、劇場などで、開演前のサウンドチェックの時はうまくいっていたアコースティックコンディションがすっかり変わってしまうのである.
例えば:
●500席の劇場であろうが、5万人収容のスポーツアリーナであろうが、聴衆が一杯になると、有る周波数では僅かに、又、別の周波数では大幅にサウンドの分布とリバーブタイムが変化してしまう。
観客の着ている衣服が音を吸収し、それにより中高域が鈍る。 最高級のコンサートホールの中でも、特別な音響設計が施されているほんの僅かな会場が、聴衆の有無に関わらず同じ特性を示すだけである。
●聴衆が入っているということは、広い反射面となっている床が部分的に覆い隠されるという事になる。
つまり、低域以外の全ての周波数の広がりや反射に、変化が生じるのである。
このことにより、コンサートの前に電子的にイコライズされた一部の反射音が、演奏中に、今度はイコライズされ過ぎるという影響を及ぼしかねない。
●空気の減衰特性は温度と湿度と関わりながら変化する。 演奏が始まって聴衆の熱気が増すこととか天候の変化により、演奏前のパラメーターとの違いが生じてきて、主に高域への影響を及ぼす。 広い会場や競技場では200ー300ヤードという距離になり、上記の影響が出やすい。(1ヤード=0.91m)
●ステージに向けられる強力な照明からの熱で、ピークの振幅と周波数が僅かに変化する。 それでイコライジングポイントが多少ずれることがある。
更に起きてくるトラブルたいていの設置業者やサウンドエンジニアはグラフィックイコライザーを使うのが好きである。 一般的にはスピーカーシステムからピンクノイズを出して、1/3オクターブのアナライザーで分析し、ノイズのピークやノッチは、見かけ上1/3、又は1/6オクターブのグラフィックイコライザーで補正される。 しかし、このテクニックは、実施の場で、その難しさが分かるだろう。
●もしも、会場のピークとディップの周波数が、アナライザーの1/3オクターブという帯域幅より狭い場合、そのピークとディップの周波数はアナライザーのセンター周波数にマッチしなくなってしまう。
●グラフィックイコライザーは各フィルターの帯域幅や中心周波数を固定してある。 これが、必ずしもサウンドシステムレスポンスのピークとディップにマッチするとは限らない。
たとえ、1/3オクターブのEQを使って1/3オクターブのアナライザーがフラットな状態を示すようにしたとしても、システムを1/3オクターブパワー帯域幅内でイコライズしたに過ぎないことが、分かるだろう。 これでは1/3オクターブより狭い帯域幅をもつピークやディップを取り除く事ができない。 システムは共振を持ち、不明瞭なサウンドとなってしまう。
パラメトリックイコライザー
グラフィックイコライザーの使い方は簡単だが、性能の良いパラメトリックイコライザーを使用しなければ最適な解決方法とならない。 中心周波数はどんな周波数でも望み通りのところへ正確にセットすることができるし、普通、帯域幅は0.1から1.0オクターブのレンジ以上に調節が可能である。
もし、よくある普通の2CHパラメトリックイコライザーを使ってしまったとする。 2つのチャンネルがお互いに補足し合うようなやり方で実験したとする。 この時、両方のチャンネルの中心周波数と帯域幅は同じにし、チャンネル2のカットと同じだけ、チャンネル1はブーストしてみる。 この二つを結合したレスポンスはSRにとって好ましくない結果となるだろう。 つまりハウリングやリンギングを起こしやすいタイムディレイが生じてしまう。 この理由は、その様に結合された2つの回路は、周波数特性はフラットになるが、本質的にはオールパスフィルターを形成し、タイムディレイが生じてしまうからである。(この説明は別項で行います。)
EQによって引き起こされたタイムディレイを無くすのには、別のタイプのパラメトリックフィルターを使わなければならない。
それはコンプリメンタリーフェーズパラメトリックイコライザーである。このタイプのイコライザーはルームレゾナンスを補正しても、タイム(フェーズ)シフトが全く起こらないであろう。 ルームレゾナンスの共振を部分的に除去することが目的ならイコライザーそのものはリンギングの一因となってはならないのである。
どうすれば、聴衆に不快感を与えずに開演間際になってピンクノイズやサイン波等を使わずに、測定調整することが出来るだろう。 それにはテストシグナルとしてハウスシステムにフィードされる音楽信号を使うのである。 レスポンスシグナルとしては普通、ハウスコンソールが設置されている場所あたりで拾われたスピーカーのアコースティックアウトプットを使う。 当然その目的は聴衆の中からピックアップしたアコースティックな信号がコンソールからの電気信号に出来るだけマッチするようEQを使いながら確かめるためである。
科学者やエンジニアは長年の間、因果関係を調査するのに2CHFFT分析法を使ってきた。
例えば、測定用の基準信号(ピンクノイズ等)にハム等がのっていたら、測定しても意味がなくなる。
それよりも良い方法は、ある1ヶ所で普通の基準信号を測定し、別のポイントで測定したレスポンスと比較してみる。 その方法で2カ所の周波数特性を確認する。 2CHFFTは複雑なコンピューター操作で周波数特性をH=B/Aとして測定する事ができる。 ライブコンサートという状況のもとではスピーカー−ルームレスポンスがH(周波数特性)となる。 ポイントAはコンソールのアウトプット、ポイントBは観客席に置かれているハウスボードのところにある測定用マイクが拾ったアコースティックシグナルである。 この経路を示した図が (最上段の図)である。注意して欲しいのはスピーカーと測定用マイクとの間に空間的な距離があるためディレイが生ずる点である。
(図)1と3二点間を測定するのに音楽をテストシグナルとして使うと2CHFFTでスピーカールームレスポンス(H)を計算できる。
会場のどの客席もフラットなレスポンスにしたいと我々は考えるが、実質的には適当と思われる場所が2、3カ所選ばれることになる。 コンサートの最中に客席の間にあるハウスミキサーコンソールのところへも測定用マイクをセットする。
従来の測定法ではライブの演奏中には、なにか有効なものを測定しだすのは、不可能に近かった。2CHFFT分析法を使うテクニックだとそれが可能になる。その理由を次ぎに掲げてみる。
・測定法がテスト用の基本となる信号(ピンクノイズや正弦波)を使用しない方法である。
・2CHFFTは800行迄の分析分解能力を持っている。
例えば5kHzのレンジを使うと6.25Hzの分解能が得られる。これはパラメトリックイコライザーがルームレゾナンスピークを正確に打ち消すことができるように調整するのに必要な分解能である。不正確な調整をしたイコライザーはレゾナンスピークを除去するどころか、実際にはノッチを付加してレゾナンスピークの一部分を取り残してしまうことになる。
・コヒーレンスファンクション(相関関数)を使うと、アナライザーのCH2で測定された信号がCH1で測定されたテスト(リファレンス)信号と一体どの程度相関関係があるのかがわかる。 コヒーレントは0〜1(0%〜100%)というレンジであらわされる。 言い換えれば、あるコヒーレンスファンクション対周波数特性はその周波数特性(スピーカー/ルーム)がどれだけ正しいかを表す尺度なのである。
ゼロコヒーレンスというのはCH1と2の信号の間になにも相関関係が無いことで、それは無意味な周波数特性である。 100パーセントコヒーレンスというのは1と2の信号の間に全面的な相関関係があり、これは正確な周波数特性測定となる。
コヒーレンスを混乱させる主な原因を次に3つ挙げてみる。
1)種々雑多なノイズや客のノイズは測定に対しては影響しないが、実際には測定を台無しにする結果につながる。
2)FFTアナライザーのタイムレコードレングスはルームリンギングモードの持続時間に比べて短いかも知れない。
大抵の2CHFFTアナライザーは両方のチャンネルのデータを同時に記録する。音響的には、確かに真実なのだが、前に述べた伝達ディレイが原因で2チャンネル間のデータは時間的な面でシンクロとはズレが生じるであろう。
その様なわけでCH1には外部のディレイラインの使用が必須となる。
次に前記のトラブルを2CHFFTアナライザーを使っていかに解決してゆくかを説明する。
1)種々雑多なノイズや客の反応音は本来ランダム現象である。FFTを使って、幾つかの連続的になったコヒーレントデータを平均してゆくと、相関関係のないノイズや客のノイズは徐々に測定値から消えて、コヒーレンスが高まってゆく。
2)もし室内に何秒かリンキングが生じたらFFTアナライザーのタイムレコードは部屋のリンキングと同じ時間に生じていなければならない。しかし、普通FFTは低域の方が長いタイムレコード許容量をもっているため、長いリバーブタイム/ルームリンギングが低域の方が確認しやすい。
3)スピーカーと測定用マイクの間に起きる伝達ディレイτにタイムオフセットが一致するようにアナライザーの2つのチャンネルをタイミング良く補正することが必須となる。こうすればダイレクトなサウンドとリバーブサウンドの最大比がえられる。実際問題としてこれを実施するにはアナライザーのCH1にディレイを挿入する。
以上が、簡単なFFTアナライザーによる音場測定法ですが、かなり専門的な言葉が出てきていますので、一般的には理解がしにくいのですが、ご理解を頂ければ幸です。
参考文献
1985 OCT15 S&VC誌より
デンマークB&K販売部長 PHILIPWHITE記
上記の関連事項の文献を提供していただいた方々に深く感謝いたします。